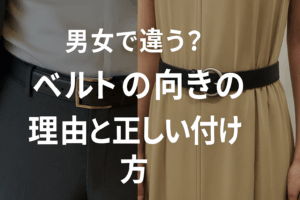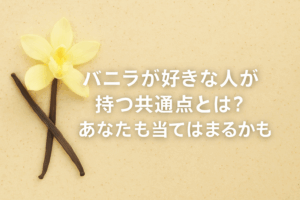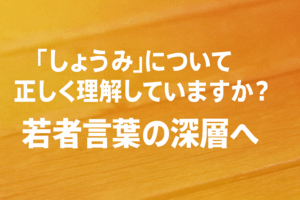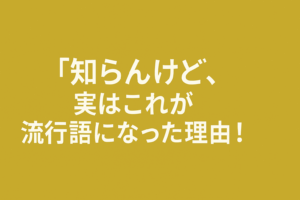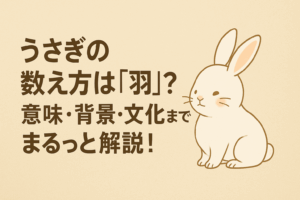「陸橋」と「跨線橋(こせんきょう)」って、よく聞くけれど何が違うの?と思ったことはありませんか。
普段の生活や旅行で何気なく目にする橋ですが、実はそれぞれに役割や使われ方があるんです。
この記事では、陸橋と跨線橋の意味・違い・読み方から、実際の写真や英語での表現まで、初心者の方にもわかりやすくまとめました。
これを読めば、「あっ、これが陸橋!」「これが跨線橋なんだ!」と楽しく知識を深められますよ。
陸橋と跨線橋の基本理解
陸橋とは?その意味と特徴

陸橋(りっきょう)は、地上の道路や川、線路などをまたぐようにして建設される橋の総称です。
特に道路交通の便をよくするために作られることが多く、車の流れをスムーズにし、渋滞を防ぐ役割があります。
- 高速道路や国道など、交通量が多い場所に多く見られる
- 歩道を併設して、歩行者も通れるものがある
- 「高架橋」という言葉で呼ばれる場合もある
つまり陸橋は「地面の上にかけられた大きな橋」であり、下を通る対象(道路・川・線路)は特に限定されません。
跨線橋とは?基本的な定義と機能

跨線橋(こせんきょう)は、「線路(鉄道)」をまたぐように作られた橋を指します。
歩行者専用の場合と、自動車も通れる場合の2種類があります。
- 歩行者用の跨線橋
駅ホーム同士をつなぐ橋としてよく見かけます。乗り換えや反対側のホームに行くときに使う構造ですね。 - 自動車が通れる跨線橋
踏切だと渋滞や事故が起きやすいため、幹線道路などでは自動車が通れる跨線橋を設け、線路と道路を立体的に交差させています。
跨線橋は、鉄道と人・車の動線を分けることで、交通の安全性を大きく高めているのです。
陸橋と跨線橋の関係性
「陸橋」という大きなくくりの中に「跨線橋」が含まれる、と考えると整理しやすいです。
- 陸橋 → 道路や川、線路などをまたぐ橋の総称
- 跨線橋 → その中でも 線路をまたぐ橋 を限定的に指す
つまり、跨線橋は陸橋の一種と言えます。
まとめ:なぜ区別が大切なの?
普段の生活では「橋」とひとまとめにされがちですが、実際は
- 「車の流れを整えるための陸橋」
- 「鉄道と人・車を安全に分けるための跨線橋」
と目的が異なります。
この違いを知っておくと、ニュースや案内板、旅行先で目にしたときに「なるほど、ここは跨線橋だから線路をまたいでいるんだな」と理解でき、日常の風景がちょっと楽しくなりますよ。
陸橋と跨線橋の読み方・使い方
陸橋の読み方と注意点
「陸橋」は、一般的に りっきょう と読みます。
ただし、日常会話や一部の地域では「りくばし」と呼ばれることもあり、少し紛らわしいのが特徴です。
- 公的な文書やニュースでは「りっきょう」が使われるのが基本
- 地元の方言や慣用的に「りくばし」と呼ぶ地域もある
- 文字通り「陸(地上)に架かる橋」という意味から来ている
このように複数の読み方が存在するため、正しい知識を知っておくと会話や文章理解で安心です。
跨線橋の正しい読み方
「跨線橋」は、正式には こせんきょう と読みます。
- 「跨ぐ(またぐ)」+「線路」+「橋」を組み合わせた言葉
- 「またぎばし」などの誤用は少ないが、読みにくい漢字のため正確に覚えておくことが大切
- 駅の案内表示やアナウンスでは必ず「こせんきょう」と呼ばれる
地域や方言による呼び方の違い
- 陸橋 → 「りくばし」 と親しみを込めて呼ぶ地域がある
- 跨線橋 → 「歩道橋」 と混同されるケースもある(特に歩行者専用の場合)
- 「高架橋」「ガード」といった別の用語で表されることもあり、地域ごとにニュアンスが違う
鉄道・道路における用語の重要性
- 鉄道利用者にとって
駅構内で「跨線橋」と書かれていれば、「あ、ホームを渡るための橋なんだ」と理解できる - ドライバーにとって
「陸橋あり」「跨線橋あり」の道路標識を見たとき、どのような橋を通るのかがイメージしやすくなる - 観光や旅行で
ガイドブックや案内板での表記を正しく理解できるので、スムーズに移動ができる
まとめ
- 陸橋は「りっきょう」が一般的、ただし「りくばし」とも呼ばれる
- 跨線橋は「こせんきょう」と読むのが正解
- 方言や慣習で呼び方が異なる場合もある
- 鉄道・道路利用の際に知っておくと便利
陸橋と跨線橋の違いを徹底解析
まずは“ひとことで”
- 陸橋:地上の交通(主に道路)を上下に分けて、車の流れを途切れさせないための橋。
- 跨線橋:線路の上をまたいで、人や車を安全に線路と分離するための橋。
※跨線橋には「歩行者用」「自動車も通るタイプ」の両方があります。
役割(目的)の違い
- 陸橋
- 渋滞を避け、信号待ちや右折・横断による“詰まり”を減らす。
- 幹線道路・バイパス・高速出入口など、車の流量が多い場所で効果大。
- 跨線橋
- 人や車を線路から離し、踏切事故のリスクをゼロに近づける。
- ダイヤ(列車の運行)を止めずに、交通を同時に流せるのが強み。
構造と設計の考え方の違い
陸橋
- 幅員:車線数+歩道(※場所により自転車道)を確保。
- 縦断勾配:大型車やバスが登れる勾配に調整。
- 接続:前後の交差点・合流部の見通しを確保し、事故を防ぐ。
跨線橋(歩行者用/自動車通行可)
- 歩行者用:階段・エレベーター・スロープで高低差をやさしく。
- 自動車通行可:線路上の最低高さ(車両限界)を満たすようクリアランス確保。
- 防音・防風:駅近では騒音対策、海辺や高所では風対策も考慮。
利用者視点の違い
陸橋
- 車にとっては「止まらず抜けられる」安心感。
- 歩道があれば、歩行者も横断歩道を待たず安全に移動可能。
跨線橋
- 歩行者用:ホーム間の乗り換えがスムーズ。ベビーカー・車いす対応の設備が鍵。
- 自動車通行可:踏切待ちがなくなり、時間の読みやすさが向上。
使われるシーンの違い(代表例)
- 陸橋:国道×市街地の交差、バイパスが住宅街をまたぐ、高速IC付近。
- 跨線橋(歩行者用):島式ホームの駅、複数ホームを行き来するターミナル駅。
- 跨線橋(自動車通行可):幹線道路と鉄道が交差/踏切渋滞や事故が多かった区間の“立体交差化”。
バリアフリーと安全性の視点
歩行者用跨線橋
- 必須ポイント:エレベーター/多目的トイレに近い動線/雨・風よけ。
- 課題:古い橋は階段のみが残るケースも。迂回距離が長いと体力的負担に。
自動車通行可の跨線橋・陸橋
- 転落防止柵・視線誘導:夜間や雨天での見え方に配慮。
- 凍結対策:橋面は地熱が伝わりにくく、冬は滑りやすい—注意喚起や路面処理が大切。
メンテナンスと更新の考え方
- 共通:点検→補修(防錆・ひび割れ補修)→必要なら架け替え。
- 駅周辺:利用者動線の変化(改札位置・再開発)に合わせ、橋の延長・増築が行われることも。
- 自動車通行可の跨線橋:交通を止められないため、夜間工事・仮橋の活用が多い。
迷いやすい関連用語の整理
- 歩道橋:人専用。線路の上なら“跨線橋(歩行者用)”でもOK。
- 高架橋:線路や道路そのものを高い位置に連続的に通す構造(連なる橋脚+橋桁のイメージ)。
- アンダーパス:下をくぐる方式(道路や歩道を“地下化”)。
- ガード:高架下の道路や通路を指す口語(地域差あり)。
ケーススタディ(イメージしやすい3例)
例1:朝の通勤ラッシュがきつい国道
- Before:平面交差で右折渋滞。
- After(陸橋):直進車が信号に捕まらず、平均所要時間が短縮。
例2:踏切で列車通過待ちが多い住宅地
- Before:踏切が1回閉まると数百メートルの車列。
- After(自動車も通る跨線橋):踏切待ちゼロ。生活道路の安全性も向上。
例3:ベビーカーでの乗り換えが大変な駅
- Before:階段のみの跨線橋で上り下りが負担。
- After(歩行者用跨線橋の改修):エレベーター設置で誰でも移動しやすく。
サッと分かる比較表
| 観点 | 陸橋 | 跨線橋(歩行者用) | 跨線橋(自動車通行可) |
|---|---|---|---|
| 主目的 | 車の流れを最適化 | 人の安全な横断 | 踏切解消+交通効率 |
| 主な場所 | 道路×道路 | 駅ホーム・線路上 | 道路×線路 |
| 利用者 | 車(+歩行者併設も) | 歩行者・ベビーカー等 | 車・歩行者 |
| 設計の肝 | 勾配・視距・合流処理 | バリアフリー・雨風対策 | クリアランス・防音・凍結 |
| 課題 | 橋面凍結・景観 | 古い設備の更新 | 工事中の交通処理 |
まとめ(使い分けのコツ)
- 車の詰まりを解きたい → 陸橋
- 線路と人・車を完全に分けたい → 跨線橋(歩行者用/自動車用のどちらか)
- 地形や周辺環境(学校・病院・商業施設)を考え、最短動線と安全を両立できる方式が最適です。
陸橋と跨線橋の歴史と進化
陸橋の歴史
- 明治〜大正時代
近代的な道路整備が進む中で、馬車や路面電車と自動車が交差するようになり、交通の安全を守るために陸橋がつくられ始めました。
当時は鉄骨やレンガを使ったシンプルな構造が多く、まだ規模は小規模でした。 - 高度経済成長期(昭和30〜40年代)
自動車の急増とともに国道・高速道路が次々と整備され、陸橋の建設ラッシュが起こります。
大きな都市部では「立体交差」が必須となり、鉄筋コンクリートを使った強固な陸橋が数多く誕生しました。 - 平成〜現在
渋滞解消だけでなく、景観・環境・バリアフリーを重視した設計が増えています。
また老朽化対策としての補強工事や耐震補強も進められ、地域ごとに再整備が行われています。
跨線橋の歴史
- 鉄道黎明期(明治時代)
鉄道が開通した当初は、駅での移動は踏切や仮設の木製通路が中心でした。
しかし列車の本数が増え、ホーム間を安全に移動する必要性から跨線橋が整備されるようになりました。 - 戦後〜昭和期
国鉄(現JR)の駅拡張に合わせて跨線橋が標準的に設置されるようになります。
この頃は木造や簡易的な鉄骨の跨線橋が多く、バリアフリーという考え方はまだありませんでした。 - 平成以降の進化
駅のバリアフリー化が推進され、跨線橋にエレベーターやエスカレーターが設置されるようになりました。
自動車が通る跨線橋も整備され、踏切を廃止して安全性を高める動きが全国に広がりました。
陸橋と跨線橋の進化の共通点
- 安全性の強化
昔は「とりあえず通れる橋」だったものが、いまは「誰もが安心して通れる橋」へと進化。 - 材料と技術の変化
木材・レンガ → 鉄骨 → 鉄筋コンクリート → プレストレストコンクリート(耐久性の高い構造)へ。 - デザイン性の向上
橋梁は「街のシンボル」や「景観の一部」としても重視され、照明や色彩計画が施されるようになりました。
近年のトレンド
- スマートシティとの連動
橋の上に防犯カメラやセンサーを設置し、交通量や安全をデータで管理。 - ユニバーサルデザイン化
高齢者・障害者・外国人旅行者など、誰でも使いやすい橋を目指した取り組み。 - 耐震・耐候性
日本は地震・豪雨が多いため、橋の長寿命化と災害対策が必須課題になっています。
まとめ
陸橋も跨線橋も、誕生した当初は「交通を通すための最低限の構造」でした。
しかし社会の変化とともに、安全・快適・美観を兼ね備えた存在へと進化しています。
今後は「地域のランドマーク」や「人とまちをつなぐ公共空間」としての役割も、さらに広がっていくでしょう。
日本における交通安全の視点から
陸橋と跨線橋の設計基準
日本の陸橋や跨線橋は、国や自治体が定める設計基準に従って建設されています。
特に重視されるのは次の点です。
- 耐震性:地震大国の日本では、揺れに強い構造が必須。阪神淡路大震災以降、橋梁の耐震補強が急速に進みました。
- 強風対策:沿岸部や高台にある橋は、強風による転倒や飛来物に備えた設計が求められます。
- クリアランス(余裕高さ):鉄道上の跨線橋では、列車が安全に通れる高さを確保。車道上では大型車が通行できるだけの高さが必要です。
交通量を考えた設計の重要性
橋の設計は、単に「かける」だけではなく、利用する人や車の量を細かく想定して決められます。
- 陸橋:交通量の多い国道や幹線道路では、複数車線+歩道を備えた大型設計が一般的。
- 跨線橋(自動車通行型):踏切渋滞が頻発する場所に設けられ、地域の交通効率を飛躍的に改善。
- 跨線橋(歩行者用):通勤通学時間に多く利用される駅では、幅広の通路やエスカレーター設置が当たり前になりつつあります。
安全な移動を支える交通インフラ
陸橋や跨線橋は「事故を未然に防ぐ」ための大切な仕組みです。
- 踏切事故の防止
跨線橋を設けることで、人と列車が直接交差するリスクを大幅に減らせます。 - 渋滞緩和による二次被害防止
陸橋によって交差点の信号待ちが減り、追突事故や歩行者事故も減少。 - 災害時の避難路
橋は時に「高台への通路」としても役立ち、津波や洪水からの避難路になることもあります。
バリアフリーとユニバーサルデザイン
交通安全を考えるとき、歩行者の安全性や快適性も欠かせません。
- 歩行者用跨線橋
エレベーター・エスカレーターの設置で、高齢者・ベビーカー利用者も安心。 - 陸橋の歩道
車道との分離柵や十分な照明を備え、夜間も安全に利用できるよう工夫されています。
地域活性化と安全の両立
陸橋や跨線橋は単なる交通設備ではなく、地域の安全と生活の質を同時に高めるインフラです。
新しい橋はデザイン性も考慮され、街の景観に調和しながら安全な移動を支えています。
まとめ
- 陸橋と跨線橋は「安全」を最優先に設計されている
- 耐震・強風・クリアランスなど、日本ならではの基準が重視される
- 交通量に応じた設計で事故や渋滞を防止
- バリアフリー化によって、誰もが安心して利用できる橋へと進化
- 地域の発展や安心した暮らしにも直結する重要なインフラ
英語での表現と国際的な視点
陸橋の英語表現
陸橋は英語でいくつかの言い方があります。地域や使う場面によって表現が異なるのがポイントです。
- Overpass(アメリカ英語)
道路が交差するときに、上を通る橋を指します。車道用の橋に使うのが一般的。 - Flyover(イギリス英語)
イギリスやインドなどでは「overpass」の代わりに「flyover」という言葉が使われます。 - Elevated road / Elevated bridge
「高架道路」を意味する表現。複数の陸橋がつながった構造を指すときに使われます。
海外旅行でレンタカーを利用する方は、「Overpass = 陸橋」と覚えておくと安心です。
跨線橋の英語表現
跨線橋は線路の上を渡る橋なので、歩行者用か車道用かで表現が少し変わります。
- Footbridge over railway(歩行者用)
線路をまたぐ歩行者専用橋。駅構内での跨線橋に当たります。 - Overhead bridge
アジア圏(シンガポール・香港など)では「歩道橋」「跨線橋」をまとめてこう呼ぶことがあります。 - Railway overpass(自動車通行可)
道路が線路の上をまたぐタイプの跨線橋。踏切の代替として使われる表現です。
日本と海外の違い
- 日本
- 鉄道駅では「跨線橋(こせんきょう)」が一般的。
- バリアフリー化が進み、エレベーターやエスカレーターが設置される例が増加。
- アメリカ・ヨーロッパ
- 歩行者専用の「footbridge」よりも、自動車用の「overpass」が圧倒的に多い。
- 郊外では鉄道より道路交通を優先する都市計画が主流。
- アジア諸国
- シンガポールやマレーシアでは「overhead bridge」という表現をよく使う。
- 高温多湿の気候のため、屋根付きの跨線橋や冷房つきの歩道橋が設置されることもある。
国際的な交通安全基準との比較
- 高さ・幅の基準
各国で異なるが、日本は鉄道車両の規格が大きいため、跨線橋の高さはやや余裕を持って設計される。 - バリアフリー基準
日本は法的にエレベーター設置が義務化された駅が多いが、海外では必ずしも義務ではない。 - 耐震・耐候性
地震が多い日本では耐震設計が必須。海外では地震よりも「積雪荷重」「風荷重」への対応が重視される地域もある。
まとめ:国際比較から見えること
- 陸橋=overpass / flyover、跨線橋=footbridge over railway という対応が基本。
- 国や地域によって呼び方も構造も異なり、「文化の違い」が反映されている。
- 日本の跨線橋は「安全性+バリアフリー+景観」を重視する点で国際的にも高く評価されている。
英語表現一覧表(日本語/米英/英英/アジア圏ほか)
| 日本語 | よみ | 米英(US) | 英英(UK) | アジア圏でよく見る表現 | 補足・使い分けメモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸橋 | りっきょう | overpass | flyover | overhead bridge(※国により) | 道路どうしの立体交差。車主体。長く連続する場合は elevated road とも。 |
| 高架道路 | こうかどうろ | elevated road / elevated highway | elevated road | elevated expressway | 道路が連続的に高架で続くイメージ。個々の橋=overpass とは区別。 |
| 歩道橋 | ほどうきょう | pedestrian bridge / footbridge | footbridge | overhead bridge(歩道橋の意味で使用される国あり) | 人専用。場所説明では pedestrian overpass とも。 |
| 跨線橋(総称) | こせんきょう | railway overpass(車道用) / footbridge over railway(歩行者用) | footbridge over railway / rail overpass | overhead bridge(国により) | 「線路をまたぐ橋」全般。用途(歩行者/車)で語を使い分け。 |
| 跨線橋(歩行者用) | こせんきょう | footbridge over railway | footbridge over railway | overhead bridge(駅構内の案内で) | 駅ホーム間の連絡橋など。駅文脈では station footbridge も自然。 |
| 跨線橋(車の通行可) | こせんきょう | railway overpass / road over rail bridge | road over rail bridge | overpass / overhead bridge | 踏切の代替となる立体交差。grade separation の一種として説明可能。 |
| 高架橋(構造物総称) | こうかきょう | viaduct | viaduct | viaduct | 連続した橋脚をもつ長大橋。道路/鉄道いずれにも用いる技術用語。 |
| 立体交差(概念) | りったいこうさ | grade separation | grade separation | grade separation | 「平面交差を避ける」という計画・設計の概念名。 |
迷ったら:
- 車が通る「道路の上の橋」= overpass(US)/flyover(UK)
- 駅の「人が線路を渡る橋」= footbridge over railway
- 車が線路をまたぐ橋= railway overpass
例文(そのまま使えるミニフレーズ)
- Take the overpass to avoid the traffic light.(信号待ちを避けるなら陸橋を使って)
- The station has a footbridge over the railway between platforms 1 and 2.(1・2番線間に跨線橋があります)
- This railway overpass replaced a busy level crossing.(混雑する踏切は跨線橋に置き換えられました)
- In the UK, “flyover” is commonly used instead of “overpass”.(英国では overpass の代わりに flyover が一般的)
よくある質問(FAQ)
Q1. 陸橋と跨線橋は同じものですか?
A. どちらも「地上の障害物をまたぐ橋」ですが、厳密には違います。
- 陸橋:道路や川・線路などをまたぐ橋の総称
- 跨線橋:その中でも特に「線路をまたぐ橋」
つまり跨線橋は陸橋の一種、と考えると整理しやすいですね。
Q2. 跨線橋には歩行者専用と車が通れるもの、両方あるのですか?
A. はい、両方あります。
- 歩行者専用:駅ホームをつなぐ橋としてよく見かけます。
- 車も通れるタイプ:踏切を解消するために作られることが多く、歩道が併設されている場合もあります。
Q3. 陸橋は歩行者も通れるの?
A. 多くの陸橋は車専用ですが、歩道がついているものもあります。
車と人が一緒に利用できるタイプもあれば、完全に分離して安全性を高めている橋もあります。
Q4. 跨線橋は必ず駅にあるの?
A. 駅には多く設置されていますが、必ずしもそうとは限りません。
地下通路を設けてホームを行き来する駅もありますし、小規模な駅では跨線橋がない場合もあります。
Q5. 跨線橋や陸橋は老朽化したらどうなるの?
A. 定期的に点検・補修が行われ、必要であれば架け替え工事が行われます。
特に古い木造の跨線橋は、鉄骨やコンクリート製に改修されている例が多いです。
Q6. 英語ではどう表現するの?
A. 基本的な対応は以下の通りです。
- 陸橋 → Overpass(米)/Flyover(英)
- 跨線橋(歩行者用) → Footbridge over railway
- 跨線橋(車道用) → Railway overpass
旅行や留学で駅を利用するときに知っておくと便利ですよ。
Q7. 陸橋と歩道橋の違いは?
A. 歩道橋は人専用の小さな橋で、車は通りません。
一方で陸橋は車道用が基本で、歩道を併設していることもあります。
Q8. どうして跨線橋や陸橋は高い位置にあるの?
A. 車や人を安全に通すためには、下を通る電車や大型車の高さを考慮する必要があります。
そのため最低限のクリアランス(余裕高さ)が確保され、結果として「高い橋」に見えるのです。
Q9. バリアフリー化は進んでいるの?
A. 近年はほとんどの新設駅で、跨線橋にエレベーターやスロープが整備されています。
ただし地方の小さな駅ではまだ階段のみの跨線橋も残っており、順次改修が進められている段階です。
Q10. 跨線橋と高架橋の違いは?
A. 跨線橋は「線路をまたぐための橋」。
高架橋は「道路や鉄道そのものを高い位置に連続的に通す橋梁」。
用途も規模も異なりますが、どちらも立体交差を可能にする大切なインフラです。
まとめ:陸橋と跨線橋の正しい理解で“安全”と“便利”に強くなる
この記事の結論
- 陸橋は、道路・川・線路など“地上の障害物”をまたぐ橋の総称。主に車の流れを途切れさせないために使われます。
- 跨線橋(こせんきょう)は、その中でも線路をまたぐ橋のこと。歩行者専用タイプと自動車が通れるタイプの両方があります。
- 読み方は「陸橋=りっきょう(地域で“りくばし”)」「跨線橋=こせんきょう」。正しく知ると案内板やニュースがぐっとわかりやすくなります。
使い分けのコツ
- 車の渋滞を避けたい/信号待ちを減らしたい → 陸橋
- 踏切をなくして安全にしたい → 跨線橋(歩行者用/自動車可)
- バリアフリーや周辺環境(学校・病院・商業施設)まで含めて、最短で安全な動線を選ぶのがベスト。
安全・設計のポイント
- 日本では耐震性・強風対策・クリアランスが重視され、駅や幹線道路ではバリアフリーが急速に進展。
- 橋は渋滞や事故を減らし、災害時の避難路としても役立つ重要インフラです。
歴史と進化
- 明治〜昭和:必要最低限の橋からスタート。
- 高度経済成長期:車社会に合わせて陸橋が大量整備。
- 平成以降:バリアフリー・景観・耐震を兼ね備えた橋へアップデート。
英語表現(海外でも迷わない)
- 陸橋:overpass(米)/flyover(英)
- 跨線橋(歩行者):footbridge over railway
- 跨線橋(自動車可):railway overpass
→ 旅行や留学、海外ニュースでも役立ちます。
誤解しやすい点の整理
- 「跨線橋=歩行者だけ」ではありません。自動車が通る跨線橋もあります。
- 「歩道橋」は人専用。「高架橋」は道路や鉄道を連続的に高い位置で通す構造のこと。
最後に(読者へのひとこと)
今日から街を歩くとき、“これは陸橋かな?それとも跨線橋?” と見分けるのがちょっと楽しくなるはず。
正しい言葉と使い分けを知っているだけで、安全に強く・移動に賢くなれますよ。