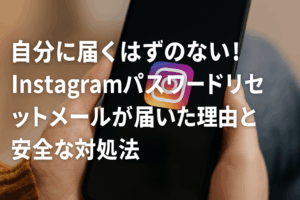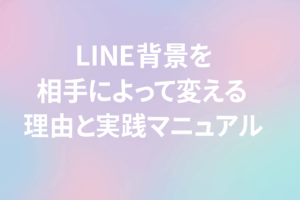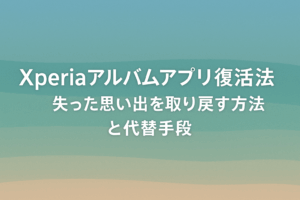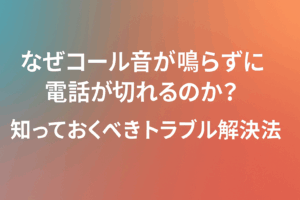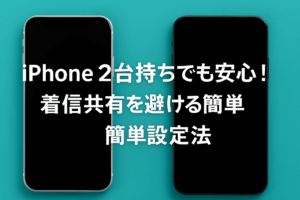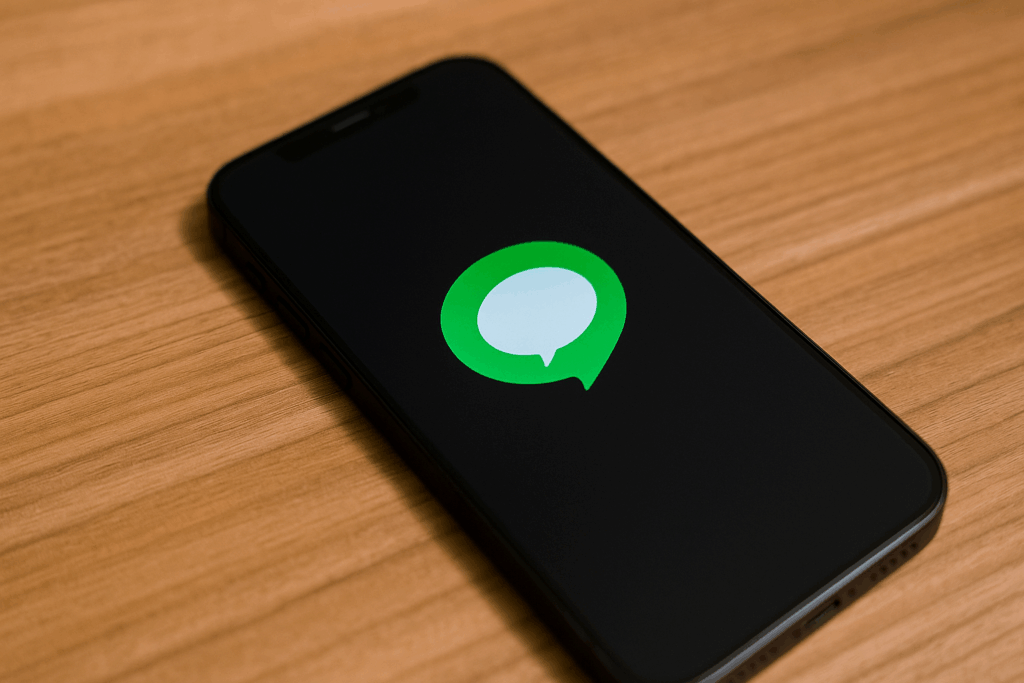
スマートフォンを持っているのに、LINEを使っていないという人が、実は少なからず存在します。友人との連絡、仕事のやりとり、家族のグループチャットなど、多くの人にとって当たり前のように使われているLINE。しかし、その便利さや浸透度とは裏腹に、「あえて使わない」「使っているけど使っていないことにしている」人たちもいます。
なぜ、スマホを持ちながらLINEを避けるのでしょうか? そこには、現代ならではの価値観や人間関係への考え方が見え隠れしています。本記事では、LINEを使わないスマホ所有者の実態や心理、代替手段、そして新しいコミュニケーション観について深掘りしていきます。
スマホは持ってるのにLINEは使わない人がいる?
スマホ普及率とLINE使用率のギャップ
日本国内において、スマートフォンの普及率は90%を超えていますが、LINEの利用率は約80%前後とされています。一見すると、ほとんどのスマホユーザーがLINEを使っているように見えますが、裏を返せば、スマホを持っていながらLINEを使っていない人が1〜2割存在するということです。
LINEを使っていない人の実際の割合
年代別で見ると、10〜30代の若年層ではほぼ全員がLINEを使用している傾向にありますが、40代以上になると徐々に使用率が下がり始め、60代では非使用率が高まります。さらに、使用していると回答していても、実際にはアカウントだけ保有していて実質使っていないケースも多いのが現状です。
| 年代別 | LINE利用率 | 非利用率(参考) |
|---|---|---|
| 10代 | 約94% | 約6% |
| 20代 | 約96% | 約4% |
| 30代 | 約93% | 約7% |
| 40代 | 約89% | 約11% |
| 50代 | 約83% | 約17% |
| 60代以上 | 約65%〜75% | 約25〜35% |
※出典:ICT総研・総務省・MMD研究所などの2023年時点のデータを基に再構成
LINE非使用者に共通する人物像・年代・傾向
LINE非使用者には以下のような特徴が見られます:
- SNS全般に距離を置いている
- 家族との連絡は電話やメールで済ませている
- 情報過多が苦手で、アプリ自体を最小限にしたい
- IT機器に対して慎重である
特に40代〜60代にかけては、LINEを“あえて使わない”という選択をする人が目立ちます。
LINEを使っていないことで感じる“少数派”の壁
「LINEやってないの?」と驚かれたり、LINEが前提の連絡網に入れなかったりと、非使用者にとって“少数派”であることの不便さや気まずさも否めません。それでもなおLINEを使わないのは、それを上回る理由や価値観があるからこそ。次章ではその理由を詳しく見ていきます。
LINEを使わない理由とは?
プライバシーや個人情報への不安
LINEを敬遠する最大の理由のひとつが「個人情報の扱い」に対する不安です。連絡先や通話履歴、写真、位置情報など、さまざまな情報がアプリを通じて管理されることに抵抗を感じる人もいます。
LINE乗っ取り・詐欺などセキュリティリスクへの警戒
過去にはLINEアカウントの乗っ取り事件や、なりすまし詐欺が話題になりました。こうしたトラブルの記憶がある人ほど、LINEに対して警戒心を抱きやすく、「使わないのが一番安全」という選択をすることもあります。
通知・即レス・グループトークなどによる“つながり疲れ”
LINEの特徴である即時性や「既読」表示、グループでのやりとりは便利な反面、人によっては大きなストレスになります。「すぐに返信しなきゃ」「既読無視と思われたくない」といったプレッシャーを避けるために、最初からLINEを使わないという判断をする人も少なくありません。
スマホに慣れていない、操作がわかりづらいという障壁
特にシニア世代に多いのが、「スマホ自体がよくわからない」「設定が難しくて使いこなせない」といった操作面での不安です。LINEの初期設定や機能の多さが“壁”となり、避けてしまうケースもあります。
公式アカウントや広告が多くて煩わしい
LINEには企業の公式アカウントや通知が多く、「広告が頻繁に届く」「関係ないメッセージが来る」といった煩わしさを感じる人もいます。シンプルなやりとりを望む人にとっては、かえって使いづらさを感じてしまうのです。
40代以上に多い?LINE離れの背景
「若者向けSNS」という距離感
LINEはもともとスマホの普及とともに若年層を中心に広がったサービスです。そのため、40代以上の世代では「LINE=若者の道具」というイメージを持ち、自然と距離を置いてしまう傾向があります。
仕事や家庭で“LINEに頼らない生活”が成り立っている
40代以上の世代は、電話・メール文化に慣れており、LINEがなくても日常生活や仕事に支障がないという人も少なくありません。特に、職場の連絡はビジネスチャットやメールで行うため、LINEを使う場面がないと感じることも。
LINE疲れを経験したことがある人の共通点
過去にグループトークでのやりとりや、既読・未読問題に疲れてしまった人の中には、その後LINEをやめたというケースもあります。「つながりすぎたくない」「自分のペースでやり取りしたい」という気持ちが強く、LINEから距離を置く選択をしているのです。
家族連絡は電話やメールで十分という価値観
LINEを使わない人の中には、「電話の方が声も聞けて安心」「文章より直接話す方が気持ちが伝わる」といった理由で、LINEを選ばない人もいます。特に親世代との連絡は電話で、子どもとの連絡はメールで、というスタイルが根強く残っています。
このように、LINEを使わない背景には、年齢層ごとの文化的・心理的な違いが大きく影響しています。次章では、LINE非使用者の“あるある”行動や、日常で感じることを紹介していきます。
LINEやってない人の“あるある”行動集
「既読スルー問題」と無縁な快適さ
LINEを使っていないことで、「既読なのに返信がない」といった誤解やプレッシャーとは無縁になります。自分のペースで連絡を取りたい人にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。
「LINE交換しよう」と言われて困る瞬間
初対面の人や職場の人から「LINE教えてください」と言われたとき、「実はやってないんです」と伝える気まずさを感じる場面もあります。驚かれたり、「今どきLINEやってないの?」と反応されたりすることも。
連絡が来ない=静かで快適なスマホライフ
LINEを入れていないことで、無駄な通知が一切来ないのも魅力です。朝起きたときの未読ゼロ、仕事中に通知で集中力が削がれないなど、スマホが本来の目的(通話や検索)に集中できるという声もあります。
代替手段で意外と不便なく暮らせる
「LINEがなくても、電話とメールで十分やっていける」という人も多くいます。むしろ、「本当に必要な人だけが連絡をくれる」という整理された人間関係を好む傾向が見られます。
周囲に驚かれることもしばしば
飲み会の誘いや仕事の連絡が「LINEで送ったよ」と言われ、「私、LINEやってないんですよ」と返すと、周囲が驚いたり、一瞬気まずい空気が流れることも。それでも、その一言で「この人、ちゃんと自分のスタンスを持ってる」と評価されることもあります。
スマホでの代替連絡手段は?
メールやSMSが意外と便利
LINEを使わない人にとって、メールやSMSはシンプルで安心できるツールです。特にSMSは電話番号さえあれば送れるため、「知らない人にIDを教える必要がない」という点でも重宝されています。
通話派の心理と習慣
「文章ではなく、声で伝えたい」という人にとっては、通話が一番自然な連絡手段です。特に年齢が上がるほど、「声を聞けることで安心する」「誤解が少ない」といった理由から電話を選ぶ傾向が強くなります。
iMessage/キャリアメール/専用アプリとの使い分け
iPhoneユーザーであればiMessage、ドコモ・au・ソフトバンクのキャリアメール、あるいはショッピングアプリ内のチャットなども代替手段として使われています。自分の利用目的に応じて、LINE以外のツールを柔軟に使い分けている人も多くいます。
ガラケーからスマホへ変えてもLINEを入れない人の理由
スマホに乗り換えても、「あえてLINEは入れない」と決めている人もいます。その理由としては、「連絡が増えるのが嫌」「操作が面倒」「余計な付き合いが増えそう」など、ガラケー時代のミニマルな生活スタイルを維持したいという思いがあるようです。
LINEは入れてるけど実質使っていない人も多い
通知オフで放置、トーク未読のまま
LINEをインストールしていても、通知をすべてオフにしていたり、トークを未読のまま放置していたりする人も多くいます。特にグループにだけ在籍している「読む専門」の人も珍しくありません。
スタンプ返信や定型文だけで“やってる風”
周囲との関係上、LINEアカウントは維持していても、スタンプや「了解です」などの定型文で済ませるケースも。実際には“積極的に活用”しているとは言えない使い方です。
アカウントだけあるがログインしていない
機種変更後に再設定していない、パスワードを忘れてしまったなどの理由で、LINEアカウント自体は存在しているが使われていない「幽霊アカウント」も一定数存在します。
一部の人としかつながっていない
親しい家族や1人だけの友人など、連絡先を限定して使っている人もいます。仕事や広い交友関係にはLINEを使わず、必要最低限だけというミニマムな活用スタイルです。
実質“LINEを使っていない”層は意外と多い
統計上は「LINE利用者」としてカウントされていても、実際には「月に一度も開かない」「返すのは数日後」という人も多く、アクティブユーザーとは呼べない層が存在します。次章では、LINEを使っていることを隠している、という人々の心理について見ていきます。
実はやってるのに“やってない”と言う人の心理
なぜ“やってないフリ”をするのか?
本当はLINEを使っているにもかかわらず、あえて「やってない」と言う人もいます。その背景には、「一部の人との関係を避けたい」「連絡手段を絞りたい」「新たなやりとりを増やしたくない」といった心理が隠れています。
“つながらない自由”を確保したいという思い
SNS疲れや即レスのプレッシャーを避けるために、「LINEを使っていないことにして、連絡を断つ」というスタンスを取る人もいます。それは単なる嘘ではなく、自分の心を守るための“自衛”の手段とも言えるでしょう。
断る口実としての「やってないです」
面識の浅い人や仕事関係の人との距離を保ちたいとき、「LINE交換しませんか?」という申し出を、自然に断るための口実として「使ってないんです」と伝える人もいます。相手に不快感を与えずにやんわり断れるため、現代の“社交辞令”の一種とも言えます。
表面的にはやっていない=真の距離感の表現
LINEの使用有無は、いまや人との距離感の指標にもなりつつあります。使っていることを隠すことで「今は関わらないでほしい」「自分の生活ペースを守りたい」という無言のメッセージを送っているのかもしれません。
LINEの機能とその魅力を再確認
トーク機能はもはや生活インフラ
個別チャットだけでなく、複数人でのグループトーク、画像や動画、位置情報の共有、既読確認機能など、トークは非常に多機能です。多くの人にとって、家族・学校・職場など日常生活に欠かせない存在となっています。
スタンプ・アルバム・ノートの活用で感情や情報を共有
文字だけでは伝えにくい感情を表現できるスタンプや、思い出をまとめられるアルバム機能、トークとは別に記録を残せるノート機能など、便利なサブ機能も充実しています。
LINE Payやクーポン、公式アカウント連携も豊富
決済やポイント管理、LINEショッピング、クーポンの配信など、生活支援サービスとしての側面も強まっています。店舗との連携も進んでおり、キャッシュレス決済ユーザーにも支持されています。
利便性がある一方で「負担」にもなり得る
これらの機能は非常に便利ですが、人によっては「多すぎてわかりにくい」「通知が多くて疲れる」「関わる範囲が広がりすぎる」など、負担に感じることもあります。
LINEを使わない人の新たなコミュニケーション観
あえて“つながらない”という選択
LINEを使わないという選択は、単に面倒だからという理由だけではありません。「誰とでもいつでもつながっている状態」に疲れた人たちが、自らの意志で“つながらない自由”を確保するという、新しい価値観に基づく行動でもあります。
情報を絞り、必要なものだけに集中する
SNSやメッセージアプリで流れてくる大量の情報から距離を置くことで、本当に必要な人・必要な情報だけに意識を向けられるという声も。これは、情報過多の時代における“情報断捨離”とも言える考え方です。
連絡手段が少ないほうが人間関係がスムーズに?
複数の連絡ツールを使いこなすより、電話とメールだけに絞ったほうが、関係が明確になり、誤解や行き違いも減るという意見もあります。気軽さよりも、“深さ”や“丁寧さ”を重視するスタンスです。
「SNSはあくまでツール」という冷静な視点
LINEをはじめとするSNSを「必須のもの」とせず、「必要に応じて使うもの」「使わなくても生きていけるもの」と捉える視点は、どこか大人びていて冷静です。このスタンスこそが、現代における“デジタルとの健全な付き合い方”の一例かもしれません。
実際のLINE非使用者の声
「なくても困らない」というリアルな実感
「最初は不安だったけど、使わなくても意外と問題ない」と感じている人は多いようです。連絡は電話とメールで足りるし、LINEを通じて入ってくる“余計な情報”がなくなってスッキリしたという声もあります。
「連絡が減って、かえって心がラクに」
LINEを使っていたころは、通知に追われたり、既読スルーへの気遣いが精神的に重荷だったという人も。「連絡が来ないこと=悪いことではない」と実感するようになったという話も印象的です。
「人間関係が整理された」
LINEをやめたことで、本当に大切な人とのやり取りだけが残ったという声も少なくありません。「惰性で続いていた関係が自然と整理された」「人付き合いが軽くなった」というポジティブな変化を語る人も。
「家族とは電話、子どもとはメールで十分」
生活スタイルによっては、LINEよりも電話やメールのほうがしっくりくるというケースもあります。特にシニア世代では、「声を聞く方が安心」「文章より言葉のトーンが伝わる」といった理由から、通話を好む傾向が見られます。
「やってないことに罪悪感を感じなくなった」
最初は「LINEを使っていないことに引け目を感じていた」という人も、次第に「自分に合った生活スタイルを優先していいんだ」と思えるようになったとのこと。これは、“同調圧力に抗う勇気”とも言えるかもしれません。
今後のコミュニケーションはどうなる?
脱SNS志向がじわじわと進行中
最近では、SNSやメッセージアプリから距離を置く「デジタル・デトックス」の流れも見られます。通知に追われる日々から脱却し、もっと自分らしい時間を過ごしたいという声が増えてきました。今後は、LINEやSNSを前提としない「非同期型のやりとり」や「リアル重視の関係性」が見直されるかもしれません。
「デジタル・デトックス(Digital Detox)」とは、
スマートフォン・SNS・インターネットなどのデジタル機器やサービスから一定期間意識的に距離を置くことを指します。
- 心身のリフレッシュ(情報過多・SNS疲れ・通知ストレスの緩和)
- 現実世界での人間関係・自然・趣味との再接続
- 睡眠の質の改善や集中力の回復
- 依存傾向のリセット
つまり、スマホやLINE、SNSなどの使用をやめたり減らしたりすることで、
「本当に必要なつながり」や「自分らしい生活リズム」を見つけ直す取り組みです。
“つながらない自由”が尊重される時代へ
これまでの「すぐに返事が必要」「既読がつく=反応しないといけない」といったプレッシャーから解放される方向へ、世の中は少しずつシフトしつつあります。今後は、“つながらない自由”が、より多くの人に理解され、尊重されるようになるでしょう。
多様なツールと心の距離感の共存
通話、メール、音声メッセージ、対面会話、そして新しいコミュニケーションアプリなど、選択肢は増え続けています。大切なのは、それらを“使いこなすこと”ではなく、“使われすぎないこと”。どの手段が一番良いかよりも、「自分に合った距離感」で選べる環境が、今後の理想的なスタイルになるでしょう。
【Q&A】LINEをやっていないと困る?
Q1. 仕事や友人との連絡が不便では?
A. 場合によっては不便と感じる場面もありますが、メールや電話で十分代替できるという声も多くあります。相手との関係性によって適した手段を使い分ければ大きな問題にはなりません。
Q2. 招待制のグループや連絡網に参加できないのでは?
A. 確かにLINE限定のグループには参加できない場合もありますが、事情を説明すればメール転送などで対応してくれるケースも。必要であれば、一時的にだけLINEを使うという選択もあります。
Q3. LINEが当たり前の世代(学生など)では浮かない?
A. 若い世代ではLINEを使わないことで「変わってる」と見られることもあるようですが、近年ではInstagramのDMやDiscord、Slackなど、他の手段で代替している人も増えており、LINE一強の時代は少しずつ変わりつつあります。
Q4. 災害時などの緊急連絡手段としては不安では?
A. LINEだけに頼らず、SMSや緊急通報アプリ、防災無線アプリなどと組み合わせることで、万一の際にも備えられます。むしろ、LINEがパンクした場合の“予備手段”を確保しておくことが重要です。
LINEを使わないことでの“困りごと”は確かに存在しますが、それを補う工夫も無数にあります。必要な時に必要な手段を選べる柔軟さこそが、これからの時代に求められる「かしこいつながり方」なのかもしれません。
まとめ:スマホ時代の“LINEを使わない選択”
無理に同調しない“選択の自由”が広がっている
LINEを使うことが当たり前のように思える時代でも、あえて使わない、または距離を置くという選択肢をとる人がいるのは、今の多様化した価値観を象徴しているとも言えます。自分にとって本当に必要か、心地よいかを判断して、ツールと付き合うことが大切です。
情報との距離を見直す良いきっかけに
LINEの非使用は、単なる「ツールを使わないこと」ではなく、「どんな情報を受け取り、どのように人と関わるか」を見直す行動でもあります。スマホ全盛の今だからこそ、一度立ち止まって自分のコミュニケーションスタイルを見つめ直す時間を持つことが、より心地よい人間関係を築く一歩になるかもしれません。
「使わない人」から見えてくる未来の形
「使わないこと」は、時に新しい時代の兆しを表しています。SNS疲れや過剰な情報のストレスから解放され、リアルな会話や心のつながりを重視する流れが、今後さらに広がっていく可能性もあるでしょう。LINEを使わない人たちの声には、現代の課題と未来のヒントが詰まっています。