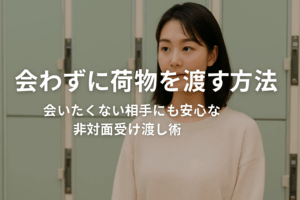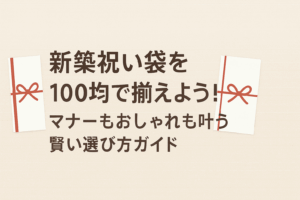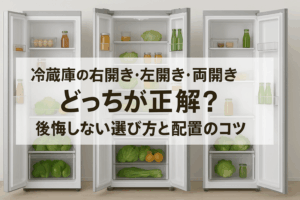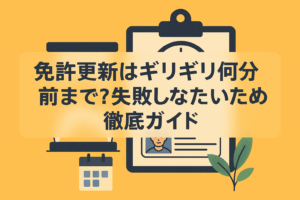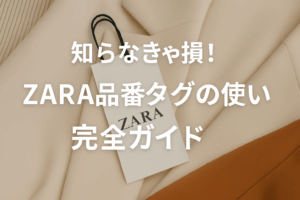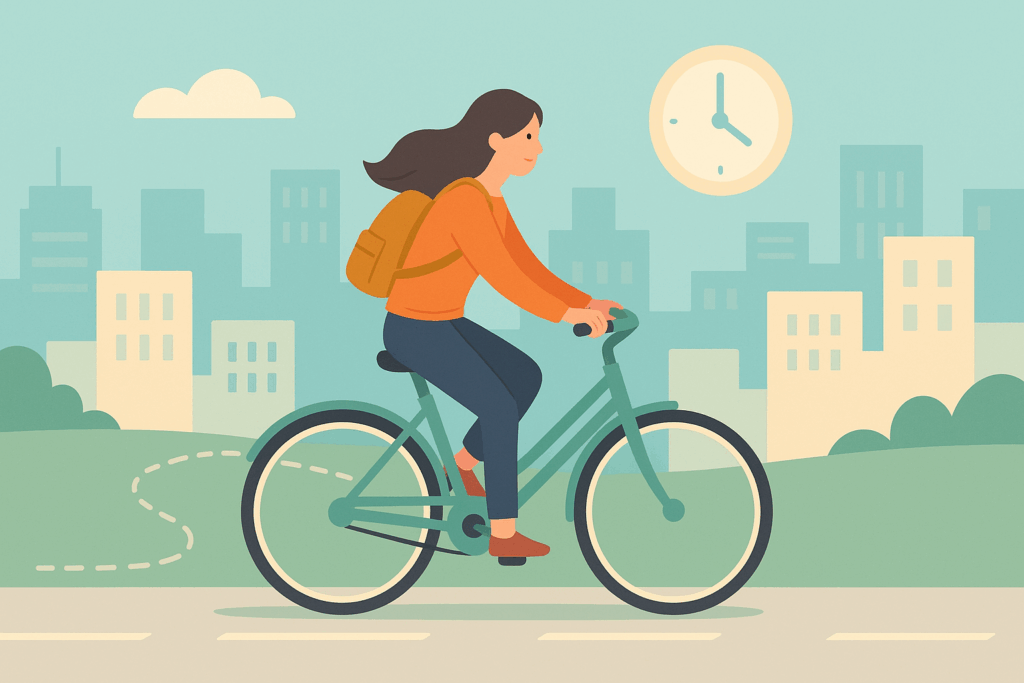
「自転車で3キロって、実際は何分かかるの?」——毎日の通学・通勤で、ふと気になりますよね。この記事では、ざっくりの目安とかんたんな計算方法、そして信号や坂道など“現実”を足した到着時刻の決め方をやさしく解説します。雨の日や小学生の通学、電動アシストの違いまで、すぐ役立つ内容にまとめました。
目次
まず結論:3kmは“10〜18分+環境補正”が目安
ポイントだけ先に
- 平地で落ち着いて走ると10〜18分が目安です。
- 信号・坂・混雑で+0〜5分ほどみておくと安心。
- 出発の余裕は5分とっておくと、遅れにくくなります。
到着時刻の考え方(かんたん)
〔計算結果〕+〔環境補正〕+〔バッファ5分〕=到着予定
※バッファとは?
「遅れやすい要素を見越して“あらかじめ足す余裕時間”。晴れ・慣れた道は+5分、雨や初見ルートは+10〜15分を目安に。」
どのくらい取ればいい?
- 普段・晴れ・慣れた道:+5分(基本)
- 信号が多い/初めての道:+7〜10分
- 雨・強風・荷物多い・子連れ:+10〜15分
- 絶対に遅れたくない用事:+15分以上(さらに早め出発)
3kmは何分?—所要時間の出し方(超シンプル計算)
基本の考え方(単位をそろえるだけ)
- 計算式:時間(分)= 距離(km) ÷ 速度(km/h) × 60
- 3kmなら:180 ÷ 速度(km/h)=分(暗算しやすい形)
- 例)12km/h → 180÷12=15分/15km/h → 180÷15=12分/18km/h → 180÷18=10分
暗算のコツ(“分/㎞”に変換)
- 1kmあたりの分数= 60÷速度
- 10km/h=6分/㎞ → 3km=18分
- 12km/h=5分/㎞ → 3km=15分
- 15km/h=4分/㎞ → 3km=12分
- 18km/h=3分20秒/㎞ → 3km=約10分
時速別・3kmの目安
| 平均速度(km/h) | 所要時間(分) |
|---|---|
| 10 | 18 |
| 12 | 15 |
| 15 | 12 |
| 18 | 10 |
| 20 | 9 |
もう少し速い/遅い場合の目安
- 8km/h(買い物帰り・向かい風など):22〜23分
- 22km/h(信号少・軽快走行):8分強(安全最優先で)
自分の“平均時速”を知る3つの方法
- 500mテスト(信号の少ない直線)
- 500mをストップウォッチで計測 → 速度(km/h)≒ 0.5 ÷(かかった時間[時])。
- 例)2分=0.0333時間 → 0.5÷0.0333 ≒ 15km/h。
- 地図アプリの“計測”機能で距離だけ測り、かかった時間を足す。
- サイクルコンピュータ/スマホ計測アプリを使い、3日分の平均をとる(1日だけはブレやすい)。
“現実補正”を数字にする簡易ルール
- 信号待ち:1本あたり約0.5〜1.5分を加算。
目安表|信号0本:+0分/1〜2本:+1〜3分/3〜5本:+3〜6分 - 小さな上り:連続する上りがある区間は+1〜3分(距離や勾配で変動・安全優先)。
- 朝夕の混雑・学童帯:人が多い道は+1〜3分。
- 雨・強風:+2〜5分(滑りやすい路面は特に慎重に)。
使い方:計算結果(180÷速度)+上の加算分+バッファ5分 = 到着目安
モデル計算(3パターン)
- 平地・信号2本・晴れ:速度15km/h(12分)+信号2本(+2分)+バッファ5分 → 19分前に出発。
- 信号多め・小さな上り:速度12km/h(15分)+信号4本(+4分)+上り(+2分)+バッファ5分 → 26分前に出発。
- 雨・混雑:速度12km/h(15分)+混雑(+2分)+雨(+3分)+バッファ7分 → 27分前に出発。
迷ったらこの3択(速度の仮置き)
- のんびり:12km/h(3km=15分)
- ふつう:15km/h(3km=12分)
- テキパキ:18km/h(3km=10分) → ここに信号・坂の加算+バッファを足せばOK。
ワークシート
- 速度(わからなければ 12/15/18 から選択):__ km/h
- 計算時間:180 ÷ __ = __ 分
- 信号加算(0.5〜1.5分×本数):__ 分
- 坂・混雑・天候の加算:__ 分
- バッファ(基本5分):__ 分
- 出発すべき“〇〇分前”= 合計 __ 分
“現実補正”をかける:信号・坂・路面・混雑
まずは考え方(かんたん)
- 到着目安=計算時間+現実補正+バッファ
- 現実補正は「信号・坂・路面・混雑」の4つを小さく足し算していくイメージです。
- 数値はあくまで目安。安全第一で、迷ったら多めに見積もりましょう。
信号・交差点の補正
- 1本あたりの目安:+0.5〜1.5分(右折・大きな交差点は上振れしやすい)
- 信号本数と加算の目安信号本数0本1〜2本3〜5本6本以上加算+0分+1〜3分+3〜6分+6分〜
右折が多いルートの工夫
- 左折中心のルートに組み替えると時間のブレが減ります。
- 右折が避けられない場所は、横断歩道で2回渡る方法も検討(安全優先)。
押しボタン式の小ワザ
- 交差点が見えたら早めに押す→待ち時間のロスを減らせます。
坂道の補正(距離×勾配でざっくり)
- 短い上りでも体感時速は低下します。下りは安全のため時間短縮に織り込まないのが基本。
- 上り区間の合計距離と加算の目安上りの合計距離100〜300m400〜800m1km以上加算+1〜2分+2〜4分+3〜6分
上りを軽くするコツ
- 上りの手前でギアを1〜2段軽く→リズムが保ちやすい。
- サドルはつま先が無理なく届く高さに。空気圧を整えると軽さが変わります。
路面・段差・路肩の補正
- 段差やレンガ舗装、砂利、工事区間、車止め等では減速・停止が増加します。
- 路面別の加算の目安路面・状況小さな段差が多いレンガ/タイル舗装砂利・工事区間路肩が狭い区間加算+1分+1〜2分+2〜3分+1分
段差の避け方
- 段差が連続する歩道より、段差の少ない車道側(ルール・安全を確認の上)へ。
- どうしても厳しい場所は押し歩きも選択肢。
混雑時間帯・人通りの補正
- 朝夕ラッシュや学童帯、商店街のピークは速度が落ちやすいです。
- 時間帯別の加算の目安状況早朝/日中のすいている時間通勤・通学帯商店街ピークイベント日加算+0〜1分+1〜3分+2〜4分+3〜5分
ペースダウンのコツ
- 人の動きが読みにくい場所では車間を広めに。抜かない・焦らないが安全で結局速いです。
クイック診断チェックリスト
- □ 信号:__本 → +0.5〜1.5分×本数 = __分
- □ 上り区間の合計:__m → 表から __分
- □ 路面:段差/工事/砂利など → +1〜3分
- □ 混雑:時間帯・商店街 → +0〜5分
→ 現実補正 合計:__分 を計算時間に足す。
補正シミュレーション(3例)
- 信号3本・小さな上り400m・通学帯
計算時間12分(15km/h)+信号(+3分)+上り(+2分)+混雑(+2分)=19分 → バッファ5分で24分前出発。 - 信号1本・平地・日中すいている
計算時間10分(18km/h)+信号(+1分)=11分 → バッファ5分で16分前出発。 - 信号5本・上り1km・商店街ピーク
計算時間15分(12km/h)+信号(+5分)+上り(+5分)+混雑(+3分)=28分 → バッファ7分で35分前出発。
停止回数を減らす3原則
- 左折中心でルート設計(右折は時間ブレとリスクが増えがち)。
- 信号が少ない道を一本裏に入れて選ぶ。
- 段差の少ない道(舗装が滑らか・自転車通行可の区間)を優先。
注意:交通ルール・通行区分は地域や道路で異なることがあります。最新情報は自治体・学校・警察などの案内でご確認ください。
電動アシストはどれだけ違う?
まずは考え方(結論)
- 発進と上りで失速しにくく、平均速度が安定しやすいのが一番の違いです。
- とくにストップ&ゴーが多い街や短い上りが点在するルートで効果を感じやすいです。
- 高速域になるほどアシストは穏やかになり(仕様上)、“巡航の最高速”より“到着時刻のブレ減少”に効きます。
到着時間のイメージ(3km・目安)
計算時間(距離÷速度×60)に、必要に応じて本記事の現実補正(信号・坂など)を足してください。
| ルート条件 | 人力の想定速度→時間 | アシスト使用の想定速度→時間 | 体感ポイント |
| 平地・信号少(0〜2本) | 15km/h → 12分 | 16〜18km/h → 10〜11分 | 巡航差は小さめ。差は1〜2分程度に留まることも。 |
| 信号多め(3〜5本) | 12〜14km/h → 13〜15分 + 待ち3〜6分 | 14〜17km/h → 11〜13分 + 待ち3〜6分 | 発進が軽く区間平均が上振れ。2〜3分短縮の場面あり。 |
| 小さな上り点在(合計400〜800m) | 12km/h → 15分 + 上り2〜4分 | 14〜16km/h → 11〜13分 + 上り1〜2分 | 上りの加算が半分程度に緩和されやすい。 |
※数値はあくまで一般目安です。安全第一で無理をしないことを前提にしてください。
ストップ&ゴーで効く理由
- 人力は停止→再加速時に脚力のピークが必要。アシストはその“つらい瞬間”を補助し、目標巡航への到達が速いため、区間平均が上がります。
- ただし信号待ちは短縮できないので、「待ち時間」そのものは別途見積もりが必要です。
坂道で効く理由
- 上りでの失速量が小さくなるため、上り区間の“加算分”が減りやすいです。たとえば、上り合計400〜800mのルートで、人力の+2〜4分がアシストだと+1〜2分になるイメージ。
効果を左右する要素(チェックリスト)
- バッテリー残量:残量が少ないと発進の力強さが控えめになる場合があります。→ 出発前に残量確認。
- 積載重量:前カゴ・チャイルドシート等で重いと立ち上がりの軽さの恩恵をより感じますが、停止距離は伸びやすいので減速早めに。
- 空気圧:低いと転がり抵抗が増えて差が出にくくなります。→ 規定空気圧に。
- タイヤと路面:太め&やわらか路面は転がり抵抗が増大。→ 路面が良い脇道の活用や、タイヤの状態チェックを。
- 気温・風:向かい風や低温で体感差が拡大することがあります(発進や上りで恩恵を感じやすい)。
アシストモードの使い分け(ECO/標準/強め)
- ECO:消費が少なく、平地巡航や信号少ルートに。到着時刻の安定はそこそこ、航続重視。
- 標準:バランス型。市街地の通勤通学に無難。
- 強め:上りや荷物多め、朝の時間厳守日に。バッテリー消費は増えるので、必要な区間だけオン/オフ。
セッティング&メンテで“安定”を伸ばす
- サドル高:低すぎるとペダリング効率が落ち、アシストの良さが活きません。つま先が無理なく届く範囲で最適化。
- ブレーキ調整:引きずりがあると常時減速状態になり平均が下がります。違和感があれば点検を。
- ライト・ベル:被視認性を上げて減速回数を減らす(譲り合いが生まれ、結果として到着が安定)。
こんなときは差が小さい/大きい
- 差が小さい:信号がほぼ無い平地直線/巡航主体の2〜3km。→ 人力15km/h vs アシスト16〜18km/hで1〜2分差に留まることも。
- 差が大きい:発進が多い旧市街/商店街、上りが細かく続く住宅街、荷物・子ども同乗。→ 2〜4分短縮の場面あり。
ミニワーク(自分のルートで計算)
- いつものルートの停止回数(信号本数)と上り合計距離を書き出す。
- 本記事の「現実補正表」で加算分を決める。
- 速度を人力(12/15/18)とアシスト(14/16/18)で2通り入れ、計算時間+加算分を比較。
- 差が2分以内ならルート最適化が優先、3分以上ならアシストの恩恵が大きい可能性。
注意:車種や仕様、地域のルールによってアシストの挙動や上限は異なります。購入・利用時は取扱説明書・メーカー案内をご確認ください。
所要時間を短縮する実践テク
まずは考え方(やさしく)
短縮のコツは「停止を減らす」と「発進を軽くする」の2本柱。これだけで1〜3分は変わります。安全第一で、無理のない範囲で取り入れてみましょう。
ルート最適化:信号少・右折回避・段差少
- 一本裏道:大きな幹線より、信号と停止が少ない裏道が安定。
- 右折は左折2回で置き換え:右折の待ち時間とブレを減らします。
- 段差の少ない道を優先:レンガ舗装や車止めが多い道は平均速度が落ちがち。
- 自転車通行可の区間や自転車道がある道を選ぶ(ルールは地域の案内で要確認)。
地図アプリの使い方
- 候補ルートを2本作成(幹線ルート/裏道ルート)。
- 信号本数と右折の回数をざっくり数える。
- 朝・夕それぞれ1回ずつ試走し、停止回数の少ないほうを採用。
走り方のコツ:一定リズムと先読み
- 一定ケイデンス(ペダルのリズム)を保つと楽に進めます。ギアはこまめに。
- 先読み減速:交差点手前は少し早めにスピードを落とすと、停止直前の時間ロスが減ります。
- 停止前にギアを軽く:再発進が軽くなり、立ち上がりがスムーズ。
- 視認性アップ:ライト点灯・明るい色の装備で「譲り合い」が生まれ、結果として停止が減ることも。
発進のミニコツ
- ペダルを足の力が入りやすい位置(前上がり)にしてからこぎ出すと、フラつきが減りやすいです。
- 車や人が多いときは無理に割り込まないほうが、結局速くて安全。
出発前30秒チェック
- 空気圧:親指で押してしっかり固いくらい(ポンプで入れるのが理想)。
- ブレーキ:左右とも引き代OK/異音なし。
- ライト:点灯・充電残量◎。
- サドル高:つま先が無理なく届く。
- 鍵・支払い:駐輪場の支払い方法(IC/QR/現金)と鍵の位置を確認。
駐輪動線の最適化:最後の1〜3分を削る
- 入口に近い枠や空きやすい時間帯を把握。
- 支払いはキャッシュレスを先に設定。アプリ対応の駐輪場なら事前登録で精算ゼロ秒。
- 鍵は出し入れしやすい場所へ固定。施錠の手順を決めて手早く(安全最優先)。
荷物の持ち方で安定スピードに
- 前カゴ+レインカバー、またはパニアで荷物を固定。肩掛けが揺れるとペースが乱れがち。
- 重い荷物は低い位置に置くとふらつきにくく、平均速度が安定します。
雨・夜は「遠回りでも簡単な道」
- 濡れた白線・マンホール・橋の継ぎ目は滑りやすいので、段差と曲がり角が少ないルートに切替。
- 明るい幹線よりも、見通しがよく停止の少ない裏道が結果的に安定することも。
7日間ミニ改善プログラム
- Day1:いつものルートを計測(停止回数/信号本数)。
- Day2:裏道ルートを作り、同条件で計測して比較。
- Day3:右折→左折2回に置換できる箇所を洗い出し。
- Day4:出発前30秒チェックをルーティン化(リストを玄関に)。
- Day5:駐輪場の入口最寄枠と精算方法を固定。
- Day6:ギアとケイデンスの“自分の快適域”を見つける。
- Day7:雨・夜ルートの安全版を1本決めておく。
クイック勝ち(今すぐ1〜3分短縮) vs 重めの改善
| 種別 | 施策 | 目安効果 |
| クイック | 右折→左折2回/鍵の位置固定/入口近くに駐輪 | 1〜3分 |
| クイック | 出発前チェック/ライト常時点灯 | 0.5〜1分+安定 |
| 重め | ルート再設計(信号少・段差少) | 1〜4分 |
| 重め | パニア導入・空気圧管理の習慣化 | 1〜2分+安定 |
見直しのコツ
- 3日平均で比較して、最短ではなく安定して遅れないルートを採用。
- シーズンや工事で状況は変わります。月1回の軽い見直しが吉。
注意:交通ルールや通行区分は地域で異なる場合があります。最優先は安全です。最新の案内は自治体・学校・警察広報でご確認ください。
距離別早見表(通勤・通学の定番)
時速別の所要時間(平地の目安)
| 距離 | 12km/h | 15km/h | 18km/h |
| 2km | 10分 | 8分 | 7分 |
| 3km | 15分 | 12分 | 10分 |
| 4km | 20分 | 16分 | 13分 |
| 5km | 25分 | 20分 | 17分 |
徒歩との比較ポイント
- 混雑路や信号が極端に多い区間では、徒歩と所要が近くなることもあります。
駅まで自転車+電車の合算の考え方
- 〔自転車時間+駐輪時間+ホームまでの移動+乗車時間〕で見積もり。乗換の待ちも忘れずに。
雨の日の安全と時短の両立
装備を整えて視認性アップ
- レインウエア/シューズカバー/高出力ライト&リアライト/反射材。
路面の注意点
- マンホール・白線・橋の継ぎ目・濡れた落ち葉は滑りやすいので、手前で速度を落としましょう。
ルート選び
- 幹線道路より、交通量の少ない裏道が安心。速度より安全を優先してください。
小学生の通学での便利さと留意点(保護者向け)
事前の下見と練習
- 一時停止・見通しの悪い交差点で“止まって左右確認”の練習。
基本装備の確認
- 反射材・ヘルメット・ベル・ライト。ランドセルカバー型の反射材も有効です。
ルールは最新を確認
- 学校の方針・自治体のローカルルールは最新の案内で確認しましょう(本記事は一般的なポイントに絞って紹介)。
通勤を“快適&スムーズ”にする装備
自転車タイプの使い分け
- ママチャリ:荷物に強く停車が多い街乗り向き。
- クロスバイク:軽快で直線が多い通勤向き。
- ミニベロ:取り回しが良く、駐輪場が狭い所で便利。
必携アクセサリー
- 高出力ライト/リアライト/泥除け/スタンド/丈夫な鍵。
バッグ運用のコツ
- 前カゴ+レインカバーまたはパニアで重心を安定。汗対策に速乾インナーや小さめタオルも。
交通ルール・マナーと最新情報の調べ方
基本の考え方(まずはここから)
- 自転車のルールは国の法令+自治体の条例+学校・地域の方針で成り立ちます。
- 情報は地域と時期で変わることがあります。この記事では一般的なポイントのみを扱い、最終確認は公式情報でお願いします。
一般的なマナー&基本装備(確認の目安)
- ライト点灯(夜間・トンネル・雨天時は早めに)/リア反射材や尾灯で被視認性を上げる。
- ベル・ブレーキ・タイヤの整備。
- 左側通行・交差点は減速と安全確認を徹底。
- ながら運転を避ける(スマホ・傘・耳をふさぐ機器など)。
- 並走・二人乗りは地域や場所で取り扱いが異なるため、標識や公式案内を確認。
- 子ども同乗は年齢・体格・装着基準等の条件がある場合があります(ヘルメット着用含め、各地域の案内を確認)。
最新情報の調べ方(3ステップ)
- 国・警察の基本指針を確認
- 例:検索キーワード → 自転車 安全 利用 ガイド ライン PDF/自転車 安全 利用 五則
- 公式サイトのPDFや広報ページを優先してチェック。
- 都道府県・市区町村のページを確認(条例・自転車保険・通行区分)
- 例:(都道府県名) 自転車 保険 義務/(市区町村名) 自転車 ルール PDF
- 自転車保険の加入義務や、通行に関するローカルルールは地域差があるため、ここで最新を確認。
- 学校・地域独自の取り決め
- (学校名) 自転車 登校 ルール/学校だより/保護者向け案内。
- 町内会・地域交通安全協会の掲示もチェック。
標識・通行区分で迷ったら(現場での判断のコツ)
- 歩道走行:標識等により認められている場合があります。「自転車通行可」表示の有無を確認。
- 自転車道・自転車専用通行帯:青い路面標示・標識を確認し、指定がある場合はそこを優先。
- 不明な場合は速度を落として安全第一、押し歩きも選択肢に。
自転車保険・防犯登録の基礎(詳細は公式で)
- 加入義務・努力義務の有無は自治体差があります。学校や勤務先の指定があるケースも。
- 対人・対物の賠償に備える観点から、必要に応じて補償内容・上限額を確認。
- 防犯登録は盗難時の照会に役立ちます。更新・引っ越し時の手続きは公式案内で確認。
雨の日の法令・マナーの考え方
- レインウエア(上下)、前後ライト常時点灯、反射材の活用が推奨です。雨天時は無理をせず、徒歩や公共交通へ切替も検討しましょう。地域によって取り扱いが異なる場合があります。
玄関に貼っておける“ルール&マナー”チェック
- □ ライト前後/反射材OK
- □ ベル・ブレーキOK
- □ 左側通行/交差点はしっかり減速
- □ スマホ・傘・耳をふさぐ機器は使わない
- □ 子ども同乗の装備・固定OK(年齢等の条件は公式を確認)
- □ その日の天気と代替手段(徒歩・公共交通)を確認
注意:ルール・標識・条例は地域と時期で変わることがあります。最終判断は公式情報に基づき、安全を最優先にしてください。
駐輪・盗難対策と“最後の1分”短縮盗難対策
まずは結論(かんたん)
- 明るく人通りのある場所に停めて、ツーロック(フレーム+車輪)+地球ロック(固定物に施錠)が基本。
- 支払いと鍵は“取り出しやすい定位置”に。駐輪場は入口より“出口寄り”が早いことも。
- 満車や雨の日に備えて第2・第3候補を地図アプリに★登録しておくと、無駄な往復が減ります。
駐輪場のタイプ別・時短と安心の早見表
| タイプ | 決済 | 早さ | 安心感 | ひとこと |
| 路面ラック(前輪差し) | 現金/IC | ◎ | ○ | 出し入れ最短。鍵の手順を固定すると速い。 |
| 二段ラック | 現金/IC | ○ | ○ | 上段は視界良いが出し入れに一手間。下段は時短。 |
| ゲート式(入出庫バー) | 券/IC/QR | △ | ◎ | 混雑時は待ちが発生。出口近くの列に並ぶ。 |
| アプリ無人型 | アプリ | ◎ | ○ | 事前登録で精算ゼロ秒。通信不良時の代替も準備。 |
| 有人 | 現金/回数券 | △ | ◎ | 防犯・案内に強い。ピークは時間に余裕を。 |
入庫→退庫“時短動線”チェック
- □ 出口に近い列/通路側の枠を選ぶ
- □ 自転車は出る方向に向けて停める(Uターンを減らす)
- □ 通路をふさがない位置に停め、押し歩きの距離を短く
- □ 鍵・IC/QRは片手で取り出せるポケットに決める
支払い・鍵まわりの“手順固定”で30秒短縮
- 入庫前にIC/QRを手に→バー通過をスムーズに。
- 停めたらフレーム+後輪にUロック等で1本目。
- 地球ロックできる場所なら、ワイヤーで固定物に2本目。
- 精算はキャッシュレス先行。アプリ対応なら事前登録で退庫が速い。
- 取り外しやすい小物(ライト・ベル・ポンプ等)は盗難防止で持ち歩く。
ツーロックの考え方:
- 強い鍵(Uロック等)でフレーム+後輪をまとめる。
- 柔らかいワイヤーは地球ロック用(フェンス・ラック等)に使うと効果的。
盗難・取り違え防止の実用ワザ
- 明るい場所・カメラの見える位置に停める。人目が多いほど抑止力。
- 車体ラベル(サドル裏・フレーム内側)に名前やマークをさりげなく。取り違え防止に◎。
- 防犯登録番号・車体シリアルをスマホに保存。写真(全体・番号部・特徴)もセットで。
- サドル・ライトなど外しやすいパーツは外して持つか、ネジを盗難対策品に。
- 停輪時間が長い場所は地球ロック優先。短時間でも施錠は必ず。
満車・雨天・イベント日の“バックアップ”
- 第2・第3駐輪場を地図に★登録(備考に「出入口・支払い方法」をメモ)。
- 1〜2本手前の別通りの駐輪場を用意しておくと、歩きが短くなることも。
- 雨の日は屋根付きや屋内の候補を先に確認。滑る床は押し歩きで。
“最後の1分”短縮テク集
- 出口寄りの枠>入口寄り(帰りが速い)
- 鍵とIC/QRは同じポケットに固定(探す時間ゼロ)
- ハンドルは真っ直ぐ・スタンドは片手で素早く下ろせる角度に
- 帰りの最初の右折はルートを替えて左折2回に(待ち時間短縮)
7日で整える“駐輪リズム”
- Day1:現行の駐輪時間を計測(入庫→施錠→退庫まで)。
- Day2:出口寄りの列に変更し、時間比較。
- Day3:鍵の種類と位置を固定(Uロック+ワイヤー/ポケット右前など)。
- Day4:アプリ決済を設定→退庫の精算時間を短縮。
- Day5:第2・第3候補を★登録。
- Day6:車体ラベル・番号写真をスマホに保存。
- Day7:雨・イベント日の代替駐輪プランを決めておく。
玄関に貼れるチェックリスト
- □ 停める場所:明るい・人通り・カメラのある所
- □ 施錠:フレーム+後輪(Uロック)/地球ロック(ワイヤー)
- □ 鍵・IC/QRの定位置OK
- □ 第2・第3候補の駐輪場メモ
- □ 退庫動線:自転車の向きは出口方向
- □ 取り違え防止ラベル・番号写真OK
注意:駐輪規則や利用条件は施設・地域で異なります。案内表示に従い、歩行者優先で安全第一に行動してください。
季節・時間帯別の走り方
夏
- 直射日光対策に帽子の下に汗止めバンド、ボトルでこまめに水分補給。木陰ルートを選びましょう。
冬・雨上がり
- 路面の凍結・濡れに注意。ライトはやや下向きにして手前をしっかり照らすと安心。
夜間
- 前後ライトに加えてサイド反射(スポークや足首バンド)で被視認性アップ。
モデルケースでイメージ(3km・環境別)
平地・信号2本
- 目安:約10〜13分
- コツ:左折中心のルートにするとブレにくいです。
信号多め+小さな上り
- 目安:約12〜16分
- コツ:上り区間は前もってギアを軽くして、一定リズムで。
雨・混雑・上り多め
- 目安:約15〜20分
- コツ:無理をしない。安全第一で、到着時刻は余裕多めに。
到着時刻の決め方(実用)
- 自分の平均に上振れ3分を足して設定すると遅れにくいです。
よくある質問(FAQ)
3kmは徒歩とどっちが早い?
- 平地なら一般的に自転車のほうが早いですが、信号や混雑が極端に多い区間は所要が近くなることもあります。
電動アシストでも渋滞は避けられる?
- 自転車の渋滞は少ないですが、歩行者優先の場所では減速が必要です。立ち上がりが軽いぶん、到着時刻は安定しやすい傾向です。
タイヤサイズで時間は変わる?
- 走り方とギア比、空気圧の影響が大きく、サイズだけでは一概に決まりません。まずは空気圧の管理を。
凍結・強風時はどう動く?
- 無理をしないのが基本。徒歩や公共交通への切替を検討し、安全を最優先にしてください。
まとめ:3kmは“計算→補正→バッファ”で遅れない
今日からできる3ステップ
- 計算:距離÷速度×60で目安時間を出す。
- 補正:信号・坂・混雑・天候を足して見積もる。
- バッファ:出発の余裕は5分。
最後に
- 毎日同じルートでも、ちょっとした工夫で到着時刻は安定します。まずは一度、信号の少ない道に入れ替えて試してみましょう。