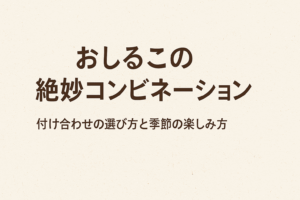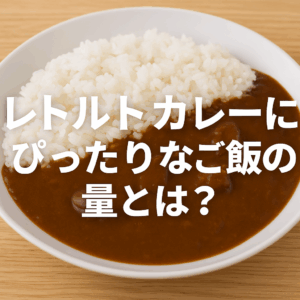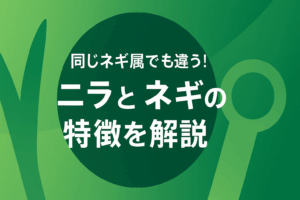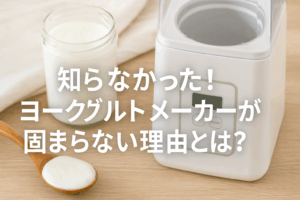お寿司は、日本を代表する食文化のひとつ。見た目も美しく、味わい深く、特別な日のごちそうとしても人気ですよね。
でも、いざ本格的なお寿司屋さんに行くとなると、「どう食べたら正解なの?」「マナーって厳しいのかな?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、初心者の方でもわかりやすく、やさしく寿司マナーをご紹介します。これを読めば、寿司をもっと気軽に、もっと楽しく味わえるようになりますよ。
はじめての寿司屋で気をつけたいこと
カウンターに座ったときは、「お願いします」と一言添えてから注文をすると丁寧な印象に。
姿勢を正して、職人さんが握りやすいよう配慮するのも大切です。
また、「今日のおすすめはありますか?」「おまかせでお願いします」など、大将とのやりとりを楽しむのも寿司屋の醍醐味です。
回転寿司やタッチパネルのあるお店では、共有スペースのマナーも大切。
注文品の横取りや、使ったお皿をレーンに戻すのは避けましょう。
お寿司の食べ方・順番とテクニック
握り寿司の正しい持ち方
握り寿司を手で食べる場合は、親指・人差し指・中指の3本でやさしくつまみます。
ネタの端が下がらないように水平に持つのがコツ。握りが崩れそうなときは、シャリの側面を軽く押さえて支えると安定します。
箸を使う場合は、ネタがずれやすいため、シャリの中央付近をやや優しく持つと崩れにくくなります。
お箸を使ってネタが落ちてしまった場合も、恥ずかしがらずに落ち着いて取り直しましょう。
醤油のスマートなつけ方のコツ
醤油をつけるときは、ネタ側を軽くなでるように醤油につけるのが理想です。
シャリを直接つけると崩れやすく、味が濃くなりすぎるので注意しましょう。
軍艦巻き(いくら・ウニなど)の場合は、上から醤油をかけるのはマナー違反とされることもあります。
このときは、小皿の醤油にガリを少し浸して、そのガリでネタの表面に醤油を塗ると上品でスマートな印象になります。
食べる順番のおすすめ
一般的におすすめされる「味の濃さ」による食べる順番は次のようになります。
- 白身魚(ひらめ、すずきなど)
- イカ・タコなどの淡泊なもの
- 赤身(マグロなど)
- 光り物(アジ、サバ、こはだなど)
- 貝類(ホタテ、赤貝など)
- こってり系(トロ、うに、いくら、穴子など)
- 巻き物(鉄火巻き、かっぱ巻きなど)
※「口直し」として、ガリをネタの合間に食べると、味のリセットができます。
ただしこの順番はあくまで一例で、「好きなものを最後に取っておく」派や「とにかく好物を最初に食べたい」派もOK!
自分のペースを大切にしながら、味の変化を楽しむのがベストです。
お寿司の「一口サイズ」問題について
にぎり寿司は基本的に一貫を一口で食べるのが理想です。
ただ、最近はサイズが大きめのお寿司も増えてきたので、無理せず2口に分けて食べてもマナー違反ではありません。
その場合、1口目をシャリから、2口目をネタ中心に食べるよう意識すると、見た目もスマートです。
できればネタが途中で垂れ下がらないよう、先にネタ側を少し噛むと食べやすくなります。
巻き寿司や細巻きのコツ
巻き寿司(鉄火巻きやかっぱ巻き)は、箸を使うのが一般的です。
特に細巻きは崩れやすいので、箸でゆっくり持ち上げ、口元まで運ぶのがポイント。
太巻きのように大きなものは、2〜3口に分けても問題ありません。
ただし、口を大きく開けて無理に頬張らないように気をつけましょう。
ネタに合った食べ方を楽しもう
・イカや白身はそのまま素材の味を感じて
・マグロ系は山わさびと合わせるのもOK
・炙り系は香りを味わうように口に入れて
・生臭さが苦手な方は「すだち」や「塩」で提供してくれるお店もおすすめ
握り寿司の食べ方は一つじゃありません。
ネタに合った食べ方・薬味・タイミングを知ると、寿司の世界がぐっと広がります。
まとめ
お寿司はシンプルなようで、実は奥が深い食べ物。
食べ方や順番、ちょっとした工夫で、味わいも体験もまったく変わってきます。
マナーやテクニックを「堅苦しいもの」ではなく、
「美味しく楽しむためのちょっとした知識」として取り入れてみてくださいね。
高級寿司店でのマナー
入店前の心構え|「敷居が高い」と感じる方へ
高級寿司店と聞くと、「マナーが厳しそう」「緊張する」と感じる方も多いと思います。
でも大丈夫。基本を押さえれば、気後れせずに楽しめます。
大切なのは「丁寧にふるまおうとする姿勢」。
完璧を目指す必要はありません。
職人さんも、お客様が気持ちよく食事できるようにと心を配ってくれています。
服装と身だしなみ|「清潔感」と「香り」への配慮
高級寿司店では、Tシャツやジャージなどのラフすぎる服装は避けた方が安心です。
男女ともに「清潔感のあるきれいめカジュアル」が基本。
特に女性は「香水や強い整髪料・柔軟剤」の香りに要注意。
寿司は繊細な香りを楽しむ料理なので、自分では気づかない匂いが他のお客様の邪魔になってしまうことも。
香りを控えめにするだけでも、印象がぐっと良くなります。
着席時のポイント|カウンターは「舞台の前列」
高級寿司店のカウンター席は、まるで“舞台の特等席”。
大将(職人さん)の手さばき、道具、ネタ、すべてが見える距離です。
・バッグは椅子の背にかけず、足元またはクロークに預ける
・ナプキンがある場合は、ひざの上にそっと広げる
・スマホは音を切って、テーブルの上に出さない
「きれいに見せよう」「周囲に気を配ろう」という意識があれば、自然と動きも上品になります。
注文と会話のバランス|大将とのやりとりもマナーの一部
高級寿司店では「おまかせ」が主流ですが、苦手なネタがある場合は最初に伝えておくとOK。
「生ものが少し苦手で…」「貝類は控えめで」など、やさしい言い方で伝えましょう。
大将との会話は、ほどよく・礼儀を持って。
フランクすぎる口調やプライベートな質問は避け、「このネタ、今が旬なんですね」といった言葉で会話を楽しむと印象が良くなります。
食べるときの所作|一口で美しく
にぎり寿司は基本的に一口でいただくのが理想。
口を大きく開けすぎず、やさしく口元に運び、ゆっくり味わいましょう。
箸で食べる場合も、シャリを崩さないように注意。
一貫を崩さずに食べられると、自然と所作も上品に見えます。
会計のマナー|「ごちそうさまでした」の一言を忘れずに
高級寿司店では、レジが見当たらないこともよくあります。
その場合は、大将やスタッフの方に「お会計をお願いします」と声をかければ大丈夫です。
支払いの際は、「ごちそうさまでした」「とても美味しかったです」と一言添えるのがマナー。
笑顔と感謝の気持ちでお店を出ると、素敵な余韻が残ります。
予約とキャンセル|お店との信頼関係を大切に
人気のある高級寿司店では、予約が数ヶ月待ちということも。
予約は早めに行い、万が一キャンセルが必要なときは、なるべく早めに連絡を入れましょう。
無断キャンセルや直前のキャンセルは、店側に大きな迷惑がかかります。
「また来たい」と思えるお店であればあるほど、信頼関係を大切にしたいですね。
ワンポイントまとめ
- 清潔感ある服装と香りへの配慮が大事
- 大将との会話は控えめ&丁寧に
- おまかせ時は「苦手なネタ」も事前に伝えよう
- 会計時は感謝の一言を忘れずに
- 予約キャンセルは早めに連絡!
「高級寿司店=かしこまる場所」と思わず、
「丁寧な気持ちを持って、寿司を楽しむ場所」と考えると、自然とマナーも身につきます。
初めての方も、リピーターの方も、ちょっとした心配りで素敵な時間を過ごせますように。
寿司をもっと楽しむためのポイント
旬のネタを知ると、寿司がもっと美味しくなる
お寿司は“旬”を味わう料理でもあります。
魚は季節によって脂の乗り方や身の締まり方が変わり、それによって味も大きく変化します。
- 春:さより・しらうお・ホタルイカ
- 夏:アジ・はも・うに・穴子
- 秋:さんま・いくら・戻りガツオ
- 冬:寒ブリ・白子・タラ・平目
このように、季節ごとに「いちばんおいしいネタ」があるんです。
お店の方に「今のおすすめはどれですか?」と聞くだけでも、新しい発見や感動が生まれますよ。
飲み物とのペアリングで味わいが変わる
寿司といえばお茶、というイメージが強いですが、実は日本酒や白ワインとの相性も抜群です。
- 白身魚(ひらめ、すずきなど):辛口の日本酒や白ワインが合う
- 赤身やトロ:ややまろやかな日本酒(純米吟醸など)
- 炙り寿司やウニ系:香り豊かな日本酒や微発泡タイプもおすすめ
もちろん、緑茶やほうじ茶も寿司の脂をすっきり流してくれる名脇役です。
「今日はお酒と合わせてみようかな」と考えるだけで、いつもとは違う楽しみ方ができます。
薬味・塩・すだちなど「通な味わい方」を試してみよう
醤油だけが寿司の味付けではありません。
最近の寿司店では、ネタに合わせて「塩」や「すだち」、「柚子胡椒」や「梅肉」など、様々な薬味や調味料で提供してくれるお店も増えています。
- 白身魚 × 塩+すだち:素材の甘みが引き立つ
- イカ × 柚子胡椒:爽やかで後味すっきり
- 炙りトロ × わさび醤油 or にんにくチップ:香ばしさUP
こうした変化を楽しむと、「これは塩のほうが美味しいかも!」と自分なりの発見ができて楽しいですよ。
大将との会話が“味”になることも
高級店やカウンター席では、大将とのちょっとしたやりとりが寿司の味をさらに深くしてくれます。
「これはどこの魚ですか?」「今が旬なんですね」
そんな一言から、お寿司の背景や仕入れへのこだわりを聞くことができたりします。
もちろん、無理に話す必要はありません。
でも、感謝や興味をもって接する姿勢があると、お店の人も喜んで教えてくれるものです。
自分なりの“楽しみルール”を見つけると通っぽくなる
寿司に正解はありません。
「いつも最後はたまごで締める」「最初にいかを頼んで、その日の鮮度を感じる」など、自分だけのルールやこだわりを見つけると、通っぽくなります。
回転寿司でも、「今日は白身縛りで食べてみよう」「軍艦巻きだけで楽しんでみよう」などのテーマを決めて楽しむのもおすすめです。
まとめ|“楽しむ力”で寿司はもっとおいしくなる
寿司はシンプルだからこそ、楽しみ方に幅がある料理です。
素材の旬を味わい、飲み物を選び、ちょっとした工夫で印象が変わります。
マナーやルールも大切ですが、何よりも「おいしいね」と感じる気持ちがいちばん大切。
自分らしい寿司の楽しみ方を、少しずつ見つけていってくださいね。
よくある寿司マナーのQ&A
Q. お寿司は手で食べてもいいの?
はい、手で食べてもまったく問題ありません。
特に握り寿司は、手で持ったほうがネタが崩れにくく、きれいに食べられるとも言われています。
ただし、手で食べるときは手指を清潔に保つ意識を忘れずに。
おしぼりで軽くふいてから、そっとつまむのがスマートです。
また、軍艦巻きや細巻きなどは崩れやすいので、箸を使うほうが無難な場合もあります。
Q. 醤油はネタ?シャリ? どこにつけるのが正解?
基本的にはネタのほうに軽くつけるのが正解です。
シャリに醤油をつけてしまうと、崩れてしまったり、味が濃くなりすぎることがあります。
軍艦巻きやトロたくなど、つけにくいネタには、
「ガリをちょっとだけ醤油に浸し、そのガリでネタの表面に塗る」テクニックが便利でスマートです。
また、お店によっては、すでに味付けされた状態で提供される握りもあるので、何もつけずにそのまま食べましょう。
Q. ガリ(しょうが)はいつ・どうやって食べるの?
ガリは「口の中をリセットする」ためのものです。
脂の多いネタを食べたあとや、味が濃いネタの合間に食べると、次のネタの風味をきちんと味わうことができます。
よく見かける失敗が、「ガリをネタに乗せて一緒に食べる」行為。
これは味を壊す可能性があり、マナーとしては避けた方がよいとされています。
Q. わさび抜きでお願いしてもいいの?
もちろん大丈夫です。
わさびが苦手な方は、「わさび抜きでお願いします」と遠慮なく伝えましょう。
おまかせコースでも、最初に「わさびが少し苦手です」と言っておくと、やさしく対応してくれるお店がほとんどです。
ただし、マグロやトロなど「わさびと相性が良い」とされるネタも多いので、少しずつチャレンジしてみてもいいかもしれませんね。
Q. 茶碗蒸しやお吸い物はいつ食べればいい?
厳密なタイミングは決まっていませんが、料理が出てきたら温かいうちにいただくのが基本です。
茶碗蒸しやお吸い物は「口直し」や「合間の小休憩」として楽しむ感覚で大丈夫。
にぎりと交互に食べるのも問題ありません。
Q. にぎり寿司を2口で食べるのはマナー違反?
一貫を一口で食べるのが理想とされていますが、最近の寿司はサイズが大きめの場合も多く、2口でもOKです。
ただし、途中でシャリやネタが崩れないよう、上品に食べる工夫が必要。
1口目でシャリ側を、2口目でネタ側を意識して食べると見た目もスマートです。
Q. 写真を撮ってもいいの?SNS投稿の注意点は?
お寿司の写真を撮る場合は、まずお店に一言確認を取りましょう。
フラッシュ撮影や、大将の動作を勝手に撮るのはNGとされることが多いです。
また、SNS投稿する際も、「店名・価格・店主の顔写真」などの情報は配慮が必要です。
料理に集中する空間なので、写真は控えめ&マナー重視で楽しみましょう。
Q. 箸の持ち方、気にされている?
意外と見られているのが箸の持ち方です。
完璧でなくてもかまいませんが、「持ち方がきれいな人は上品に見える」と好印象を持たれることも多いです。
お箸のマナーで避けたい行動もあります。
- 刺し箸(寿司を突き刺す)
- 渡し箸(箸を器の上に横に置く)
- 探り箸(ネタを箸でいじる)
これらを避けるだけでも、所作がぐっと美しくなりますよ。
Q. 回転寿司でもマナーってあるの?
もちろんあります。
回転寿司は気軽に楽しめる場所ですが、共有スペースでもあるため、次のようなマナーを意識すると好印象です。
- 取ったお皿を戻さない
- 流れているネタに指をかけない
- タッチパネルやレーンを丁寧に扱う
- お子さま連れの場合は、周囲に配慮
誰でも使う場だからこそ、「ちょっとの気遣い」で素敵な空間になります。
まとめ|よくある疑問は“楽しみの入口”
こうした素朴な疑問をひとつずつ解消していくことで、
寿司がもっと身近に、もっと楽しく感じられるようになります。
「これ、聞いても大丈夫かな?」と思うようなことも、
あらかじめ知っておけば安心して食事を楽しめます。
マナーを“制限”と感じず、「美味しさを引き出すための知恵」として味わってみてくださいね。
子どもと寿司を食べに行くときのマナー
1. お店選びで8割決まる!安心して楽しめる寿司店とは
子どもと一緒に外食するときは、「お店選び」がとても大切です。
せっかくの楽しい時間も、落ち着けない空間では親も子どもも疲れてしまいますよね。
おすすめは…
- 回転寿司やファミリー向け寿司店(タッチパネル注文やキッズメニューあり)
- 座敷・個室がある店(お子さま連れOKと明記されている店)
- お昼営業の寿司屋(比較的カジュアルで入りやすい)
高級寿司店など、静かで格式の高いお店に行く場合は、子どもの年齢や状況に合わせて慎重に判断を。
「今日はちょっと難しそうだな」と感じたら、無理せず次の機会に楽しむのも立派なマナーです。
2. 注文や食べ方の工夫で子どもも大人も快適に
子どもが寿司を楽しめるように、事前の工夫や声かけでトラブルを減らせます。
◎食べやすい&人気のネタ
- たまご、納豆巻き、ツナマヨ、コーン、サーモン、かっぱ巻きなど
→ 味がやさしく、見た目にも親しみやすいものが◎
◎注文時のひと工夫
- 「一口サイズでお願いします」や「わさび抜きで」など、お店に伝えると安心
- 「お箸じゃなくフォークにします」も遠慮なくOK
◎小さな取り皿を使って分ける
- 1貫ずつ取り分けるだけでも、親の負担がぐっと減ります
3. 食事中の“ちょっとしたマナー”を子どもと一緒に
子どもにとっても、外食は“学びの場”です。
完璧でなくてもいいので、楽しみながらマナーを伝えるきっかけにしてみましょう。
やさしく伝えたいポイント:
- 食べ物で遊ばない
- 回転レーンに触らない(手を出さない)
- 大きな声を出しすぎない
- 自分の席に座る・動き回らない
- 食べ終わったお皿はきれいに重ねる練習を
大人が丁寧に食べる姿を見せてあげるだけでも、自然とマナーは身についていきます。
「上手に食べられたね!」と声をかけてあげることも大切です。
4. トイレ・グズり対策など “事前準備”で安心
特に小さなお子さんを連れて行く場合は、事前の備えでグッと余裕が生まれます。
- 出かける前にトイレを済ませる
- お気に入りの絵本や静かな遊び道具を1つ持参
- すぐ食べられるもの(おにぎりやゼリーなど)を予備で用意
- 長時間にならないよう、あらかじめ「〇〇分だけね」と伝えておく
「子どもがぐずってしまったら、無理せず早めに出る」判断も大切です。
親が気を張りすぎると疲れてしまうので、“今日は経験値アップ”くらいの気持ちでOKです。
5. 高級店や大人向けの寿司屋ではどうする?
もし、記念日や親族の集まりなどで高級店に行くことになった場合は…
- あらかじめ「子ども連れである」ことをお店に伝える
- 「お子さま対応できますか?」と相談する
- 静かにできる年齢であれば「今日はちょっと大人の場所だよ」と教えてあげる
無理をせず、子どもが落ち着いて過ごせる年齢になってからチャレンジするのもひとつの選択です。
お店も快く対応してくれる場合があるので、事前の連絡がカギになります。
まとめ|「おいしいね」と言い合える空間を大切に
子どもとの寿司時間は、ただ食べるだけではなく、
「食の楽しさ」「作ってくれた人への感謝」「一緒に食べることの嬉しさ」を伝えられる時間でもあります。
- お店選びは子どもに合わせて
- 注文や席の工夫でトラブル回避
- 完璧じゃなくてOK!少しずつマナーを伝えていく
- お店や周囲への配慮も忘れずに
「楽しかったね」「また行こうね」
そんな会話で締めくくられるような、あたたかい外食時間になりますように。
やってはいけない寿司マナーNG集
NG① シャリを残す・ネタだけを食べる
「糖質控えめにしたいから…」と、シャリを残してネタだけ食べる行為は、
寿司職人さんにとっては「自分の仕事を否定されたような気持ちになる」こともある、実はとても失礼な行為です。
お寿司は、ネタとシャリの一体感やバランスを大切にした料理。
どうしてもご飯を少なめにしたいときは、注文時に「シャリ少なめでお願いします」と伝えるのがスマートです。
NG② 醤油をたっぷりつけてネタが浸る
お寿司を「醤油だく」にしてしまうと、ネタの繊細な味が消えてしまい、職人さんの工夫も台無しになります。
また、シャリに直接つけて崩れてしまったり、皿にベチャッと垂れると、見た目もあまり美しくありません。
おすすめは…
- ネタの端を軽くつける(“なでる”くらいがベスト)
- 軍艦巻きはガリを使って表面に塗る
- 「味がついています」と言われた寿司はそのまま食べる
上品で美しい食べ方ができると、それだけで食の印象もグッと変わります。
NG③ ガリを寿司に乗せて一緒に食べる
ガリは“口直し”のための存在です。
ネタと一緒に食べると、その本来の役割が果たせなくなってしまいますし、味のバランスも崩れます。
「味に変化をつけたいから」と思う方もいるかもしれませんが、
その場合はネタに合う薬味(塩・すだち・柚子胡椒など)を選ぶ方がスマートです。
NG④ カウンターで肘をつく・大声で話す
高級寿司店のカウンター席は、“寿司を観る・感じる”舞台の最前列のようなもの。
そこで肘をついたり、大声で話すのは、周囲のお客様や職人さんにとっても迷惑になりやすいです。
楽しい気持ちは大事ですが、静かな空間の雰囲気に合わせた「ちょっと大人な所作」を意識してみましょう。
NG⑤ ネタを箸で引きはがして裏返す
「ネタに醤油をつけるため」に、わざわざネタとシャリを分解するのは、
職人さんが丁寧に仕上げたバランスを崩すことになってしまいます。
どうしてもネタにだけ醤油をつけたい場合は、手で寿司を軽くひっくり返してネタ側を下にする食べ方が推奨されます。
箸でムリにネタをはがすのは見た目にも不格好なので避けましょう。
NG⑥ 食べながらスマホを操作・写真を撮り続ける
最近は「映え」目的で写真を撮る方も増えましたが、
スマホを操作しながら食事をする行為や、写真撮影に集中しすぎることはマナー違反とされることもあります。
最低限守りたいポイント:
- 撮影は一度だけ、短時間で
- お店や大将には一声かけて許可をとる
- フラッシュ・連写・音が鳴る設定は避ける
- 他のお客様が写り込まないよう配慮する
「寿司の写真より、あなたの“美味しい顔”を見せてほしい」
そんな声もあるほど、その場を味わうことが何より大切です。
NG⑦ お箸マナーを意識しない(渡し箸・指し箸・探り箸など)
お寿司に限らず、和食全般においてお箸のマナーはとても重要です。
避けたい使い方:
- 渡し箸:お皿の上に箸を渡して置く
- 指し箸:箸で人や料理を指す
- 探り箸:ネタを箸でつついたり選びすぎる
- 握り箸:箸をグーで持つような形で力を入れて使う
「きれいな箸づかい」は、それだけで印象を大きく変えます。
完璧を目指す必要はありませんが、丁寧に使おうという姿勢が伝わるだけでもOKです。
まとめ|NGマナーを知ることは「お寿司をもっと楽しむ第一歩」
お寿司のマナーは、難しいルールではなく、
「おいしく食べるための工夫」や「思いやりの表現」だと考えてみましょう。
やってはいけない行為を知っておくことで、
お店の方にも、周囲の人にも、そして何より自分自身にも気持ちのいい時間が訪れます。
- 「きれいに食べるって気持ちいい」
- 「また来たいと思ってもらえる振る舞いをしたい」
- 「子どもにも伝えられるマナーを身につけたい」
そんな気持ちがあれば、マナーは自然と身についていきます。
ぜひ、今回ご紹介したポイントを、次のお寿司の時間に活かしてみてくださいね。
まとめ|寿司を美しく、美味しくいただこう
マナーを知ることは、自信を持って楽しむ第一歩
「マナー」と聞くと、堅苦しくて窮屈なもの…と思ってしまう方も多いかもしれません。
でも、寿司のマナーは“美味しさをもっと引き出すための知恵”であり、“お店や人との関係を豊かにする作法”でもあります。
ほんの少しの気配りで、食べ方も所作もぐっと美しくなります。
そして、「自分はきちんと知っている」という自信が、食事の時間をもっと自由で楽しいものに変えてくれるはずです。
所作ひとつで「味わい」が変わる
例えば、ネタにそっと醤油をつける動作。
シャリを崩さないように気を配る仕草。
「美味しいですね」と職人さんに伝えるその一言。
そのすべてが、“ただの食事”を“美しい体験”へと変える要素になっているのです。
寿司はシンプルだからこそ、そこに込められた気遣いや心のゆとりが、より大切に映ります。
正しいマナーは「食べる人」への思いやりでもある
マナーとは、「相手が気持ちよく過ごせるように」するためのもの。
それは、お寿司を握ってくれた人に対しても、同じ空間で過ごす他のお客様に対しても、同様です。
そして、何よりも大切なのは、自分自身もその空間で心地よくいられること。
「正しく」ではなく、「やさしく」「きれいに」いただくことで、自然と周囲にも気配りが伝わります。
あなたらしい寿司の楽しみ方を見つけて
この記事でご紹介したマナーや楽しみ方は、“正解”の一例にすぎません。
最終的には、「どうすれば自分らしく、気持ちよく楽しめるか?」がいちばん大切です。
・旬のネタを味わうのが好きな人
・大将との会話を楽しみにしている人
・回転寿司で気軽に食べるのが幸せな人
・おまかせに身をゆだねるのが楽しい人
どのスタイルでも大丈夫。
大切なのは、食を通じて心が豊かになる時間をつくることです。
最後にひとこと|「また食べたい」と思える経験に
お寿司は、日本の誇る食文化。
だからこそ、食べ方やマナーを知っている人は、それだけで一目置かれる存在になれます。
でも、いちばん大事なのは…
「また来たい」「また誰かと一緒に食べたい」と思える食事だったかどうか。
マナーは、堅苦しく守るものではなく、誰かと心地よく過ごすための“やさしい工夫”。
今日学んだことを少しずつ実践していけば、きっと次の寿司時間はもっと豊かになるはずです。